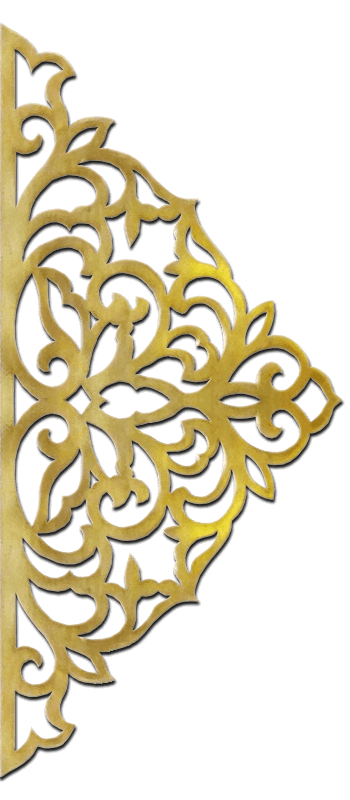日本において金属が使われだし、その加工技術が発達するのは大陸の影響を受けた弥生時代である。青銅製の銅鐸、銅剣、銅矛、また鉄器なども生産され、銅鏡の製作も盛んにされた。
初期の古墳からは朝鮮渡来の馬具や装身具が出土しているが、武具類など日本製と考えられる彫金、鋳金の優品が時代をくだった古墳より出土していることから、金工品で身を飾る風習が支配階級の間で盛んになり、技術が発達したと思われる。
また、仏教伝来により、仏像、建築金具、仏器、荘厳具、梵鐘等を作る鍛金、鋳金、彫金の精巧な技術が興った。平安時代の密教法具、鎌倉時代へと続く宝塔、舎利塔、経巻、経箱、箱類金具等、仏教関係には精巧なものが数多く、宝冠、光背、天蓋等には蹴彫、透彫などの技法が駆使されている。
意匠的にみると、古墳期以降は甲冑、太刀の外装に日本的な特色が強くなり、平安後期以降になると日本風の華やかさが見られるようになる。建築の錺金具も同様に、鎌倉、室町、桃山と、それぞれの時代色豊かな意匠、技法が興り、日本独自の金工美を味わうことのできる江戸期の装剣金具へと続く。
装身具においては、もともと金属自体に装身具的意義があったのだが、時代が進むにつれて金、銀、白金が貴金属として重要な素材とされるようになり、装剣金具を飾る合金の発達を促した。すなわち赤銅、四分一、青金、山金等、多様な合金が色彩効果を上げた。この技術が明治以降、櫛、簪、帯留、キセル、文房具、袋物口金等に用いられ、華麗な細工物が生まれることになる。
さて現代では、錺金具製作においてもご多聞にもれず機械化が浸透し、新しい生産方式が出現している。イタリア式蝋型鋳造、ダイキャスト小物における遠心鋳造、型プレス、電鋳、エッチング等であるが、これらは大量生産方式の申し子以外の何物でもない。
本来錺金具とは本質的に大量生産すべき物ではなく、手作りなるが故に、たとえ同じモチーフのものでも微妙に異なり、優雅な気品に満ち、立体感のある空間を構成することが可能なのである。